菌ちゃん農法との出会い

2022年6月から生ごみコンポスト生活をはじめて、なんとなく「微生物っていい存在だな」という感覚で家庭菜園を続けていました。
2024年夏、菌ちゃん先生こと吉田俊道先生の本と出会いましたが、そのときは実践しませんでした。なぜなら、土づくりに2〜3ヶ月かかるから。当時のわたしは「すぐに植え付けして育てたい!」という気持ちが強かったんです。
ですが、2025年の夏、菌ちゃん農法はじめました!
その年は雨が少なく、とても暑い夏。畑やプランターの植物たちへの水やりが大変で、「この暑さ、何かに活かせないかな」と思ったんです。
そんなとき、育ちの悪い植物たちに見切りをつけて、古土をシートに広げて日光消毒しました。
その大量の土をどうしようかと考えていたとき、ふと「菌ちゃん農法」を思い出したんです。
「今は暑いし、プランターを増やしたくない。でも、時間をかけて古土を有効活用するのはいいかも!」
そう思った瞬間、夏の庭仕事に少し嫌気がさしていた気持ちが、ふっと明るくなったのを今でも覚えています。
菌ちゃん農法を学びながら実践
そこからは、本を読んだり、YouTubeで菌ちゃん農法を検索しては動画をひたすら見たり聞いたりしていました。YouTubeだと情報が新鮮でないこともありましたので、後にオンライン講座を受講しました。しっかりと学びたい方はオンライン講座がおすすめです。
ここからは本や動画で学んだことと実践した内容をまとめていきたいと思います。
菌ちゃん農法は糸状菌ファースト
菌ちゃん先生(吉田俊道先生)は生ごみを使った農法の本を書かれたりと菌について研究を尽くされています。
その菌ちゃん先生が元気な無農薬野菜をつくるには糸状菌を生かすことが大事だと仰られています。多くの方が「糸状菌とはなんぞや?」となると思います。わたしもそうでした。
糸状菌とは菌類の一種で、細長い糸状の菌糸で構成される微生物の総称。
糸状菌が食べる(分解する)ものは木や落ち葉、固い刈草、竹、もみ殻など。
動画の中で、菌ちゃん先生が「やがて束になってキノコになる」と仰っていました。ということはキノコの赤ちゃんみたいなものかな?と思いハッとしました。
わたしは登山が趣味でよく山へ訪れるのですが、山で見かけるキノコは倒木(死んでいる木)にしか生えていないんです。

立ち枯れた木に大きなキノコ
実際に見た経験と重なり、とても理解が早かったです。
理解したらとにかく実践したくなる!その前に糸状菌ちゃんを増やすには、糸状菌ちゃんの好きなもの(エサ)を理解する必要がありますよね!
糸状菌ちゃんのエサになるもの
炭素分が多い有機物が糸状菌のエサになります。これなら庭にありそう!近くの公園にあるかも!?という視点で読んでいただけたらと思います。
刈草
セイタカアワダチソウなどの大型雑草や、ねこじゃらしのようなイネ科の葉がツンツンした固い雑草を数ヶ月野ざらしにしたもの。
もみ殻
窒素分が少なく、炭素分が多いうえに、空気をよく含むので糸状菌が増えやすい。新鮮なものはお水をはじいてしまうそうで、半年ほど雨ざらしにしてから使う。表面に白く糸状菌が付着しているとベスト。
竹
糸状菌が付きやすい。鉄など微量要素にも富む。野ざらしにしたものはもちろん、竹については切ったものをすぐエサにできるとのこと。その際は1〜10cmほど細かくして使う。
落ち葉
落ちたばかりのものよりも数ヶ月野ざらしにした黒くなった落ち葉が最高とよく動画でも紹介されています。山道の溝にたまっているような落ち葉はすでに糸状菌が付いていることもあるのでエサに使いやすい。
木
長さ3〜5cmほどのチップ状になったものが便利。切ってから数ヶ月野ざらしにして、糸状菌が付き始めたものだとよりよい。
繊維くず
着古した衣服。ただし天然繊維100%のものを使う。(綿や麻、ウールなど)

えー!こんなものも食べるのか?!と驚きましたが、衣服に使われる天然繊維は元を辿れば植物ですもんね。菌ちゃん農法ってこういう気づきがあって楽しいです♪
菌ちゃん(糸状菌)のエサ集め
 エサが分かったところでエサ集めが始まりました。わが家では、家庭菜園やガーデニングで出るの残渣、庭にはえているツンツンした葉の雑草、落ち葉、もみ殻、使い古したインナーが使えそうでした。
エサが分かったところでエサ集めが始まりました。わが家では、家庭菜園やガーデニングで出るの残渣、庭にはえているツンツンした葉の雑草、落ち葉、もみ殻、使い古したインナーが使えそうでした。
どれも一旦雨ざらしにしてからの使うので、集めて数ヶ月雨ざらしにしました。
太陽にも雨にも当てる、というよりも放置します。
そうするといい具合に枯れてきます。
パキッと折れるくらいがいいと思います。中に芯があるようだとまだ早いです。

集めた菌ちゃんのエサ
エサが集まったら次は、畝づくりです。
菌ちゃん農法 畝づくり
 わたしは欲張って畑、花壇、プランターと3パターンで作りました。
わたしは欲張って畑、花壇、プランターと3パターンで作りました。
皆さんもこれならできそう!と思えるものからスタートしてみてください!
畑
菌ちゃん農法で一番大変なのが高畝(一番低いところから50cmほどの高さ)を作ることです。
けれど、この高さが重要だと菌ちゃん先生(吉田先生)は仰られます。
畝づくり初心者ですが、できるだけ忠実に作りました。
父にも手伝ってもらいましたが、ありがたいことに実家の土は柔らかかったので、ほぼ女性一人(私のちから)で作ることが出来ました。

真夏なので空調服を着て取り組みました。
花壇
畑と同じく高畝を花壇の中に作っていきます。
壁沿いの限られたスペースで作業になるので、変な姿勢になったり少し作りにくかったですが、畑に比べると小さいので、女性でも大丈夫だと思います。

菌ちゃん農法 花壇バージョン
プランター
畝の代わりに高さのある深型のプランターを用意しましょう。
高さ40cm以上がおすすめです。ない場合は、大きな肥料袋で代用できるそうです。
わたしは不織布プランター30リットルがあったので、こちらを使用しました。

不織布プランター30L
プランターの一番下には必ず排水をよくするために軽石や小枝、もみ殻を入れます。
(プランターに付属している排水ネットがありましたら、それも敷きます。)
軽石の場合は5cm程度、小枝などかさばるものは5~10cmくらいを目安にいれます。
わたしは一番下には庭の木の木くずなど雑草よりも少し硬そうなものを敷き詰めました。

一番下に小枝を入れてみた
中に入れる土は肥料のない使い古した土を湿らせてから使います。
排水がよい土がいいので、排水が悪い場合はもみ殻を1~2割入れると良いそうです。
わたしは野菜を育て終わった土を利用しました。

畑と花壇の高畝の下にも大きめの木など菌ちゃんのエサになるものを埋めておくとエサがゆっくり分解されて菌ちゃんが長く元気でいてくれるそうです。
菌ちゃん農法 エサをのせる
畑の畝、花壇の畝、プランターどれも最後に菌ちゃん(糸状菌)のエサをのせます。
畑

菌ちゃんのエサをのせた様子
実家なのでたくさんの種類のエサがあったので色々混ぜて入れてみました。
すでに糸状菌らしいものがついているものがあると尚良いそうです。
のせ方は出来るだけ均等に、植物を植えるときに邪魔にならないように大きなものはカットしてのせました。のせたら少し土をのせてエサと土が交わうようにします。
花壇

花壇の菌ちゃん高畝にエサをのせた
エサは庭に生えていた雑草、育てた野菜の残渣を雨ざらしにしたものを使いました。
ボロボロになった木くずもエサになりそうなので入れてみました。
出来だけ均等に、植物を植えるときに邪魔にならないように大きなものはカットしてのせました。
のせたら少し土をのせてエサと土が交わうようにします。

畑と花壇はマルチを被せる前に一雨当てます。
ジョーロなどよりも時間をかけて雨に当てるほうが水分が行き渡るそうです。
プランター
 花壇と同じく庭の雑草や育てた野菜の残渣、それから使い古したインナー(綿100%)を雨ざらしにしたものをエサとして使いました。のせたら少し土をのせてエサと土が交わうようにします。
花壇と同じく庭の雑草や育てた野菜の残渣、それから使い古したインナー(綿100%)を雨ざらしにしたものをエサとして使いました。のせたら少し土をのせてエサと土が交わうようにします。
もしエサがからからだったら少しジョウロなどで水をかけて湿らせましょう。
菌ちゃん農法 マルチで覆う
 立派な畝が出来てエサをのせ、十分に湿らせたら、いよいよ最後の工程のマルチ作業です。
立派な畝が出来てエサをのせ、十分に湿らせたら、いよいよ最後の工程のマルチ作業です。
畑
畝全体に覆いかぶさるくらいの大きさのマルチを用意して上から被せていきます。
次にマルチ押さえ(トンボ)を差し込み、マルチを固定します。

2025.8.15 完了!
マルチの上に土や大きめの石をのせていきます。
マルチが風で飛ばないようにすることと、乾燥を防ぐためです。
そうすることで野菜づくりに大切な菌ちゃん(糸状菌)を繁殖させることができるそうです。
土は20~30cmほどの間隔をあけて畝の両端にジグザグでのせるとより良いみたいです。

重しがあると毛細管現象でその部分は乾きにくく、他は乾きやすい。そうしてメリハリをつけるのも菌ちゃん(糸状菌)にはいいそうですよ!
最後に忘れてはいけない、空気を入れるための穴をあけて終了です!
花壇
花壇も畑のマルチの覆い方と同じです。
畝を覆える大きさのマルチを用意してしっかり包み込んでマルチ押さえ(トンボ)を差し込み固定します。
マルチの上に土や大きめの石をのせて、マルチが風で飛ばないようにすることと、乾燥を防ぎます。
そうすることで野菜づくりに大切な菌ちゃん(糸状菌)を繁殖させることができるそうです。
わたしは庭にあった大きめの石やレンガを使いました。

2025.9.8 完了!
最後に空気を入れる穴をあけて終了です!
プランター
黒マルチを被せます。マルチがなければ、大きな黒いごみ袋でもOK。
マルチを被せたら風で飛ばされないよう紐で縛ります。そして、最後に空気が入るように穴を開けす。このまま3ヶ月間放置します。保管場所は直射日光や雨が直接当たらない軒下がいいようです。

2025.10.27 完了!
菌ちゃん農法実践中!2025.11
こちらは作業ごとに更新している記事となります。
2025.11月現在は畑、花壇、プランター3つパターンのすべての工程が終わり、あとは菌ちゃん(糸状菌)が育つのを待っている状態です。
とってもワクワクしながら菌ちゃん育成中です。
菌ちゃん先生は「菌ちゃんがんばってね~♪」と声をけると菌ちゃんが増えやすいと言われていたので、愛着をもって接しています。
たくさん菌ちゃんが増えて健康野菜が食べれるまで気長に待とうと思います🍁
ここまで読んでくださってありがとうございます。
Instagramでもリアルタイムで記録を行なっております。

よろしければフォローしていだだけたら嬉しいです♪
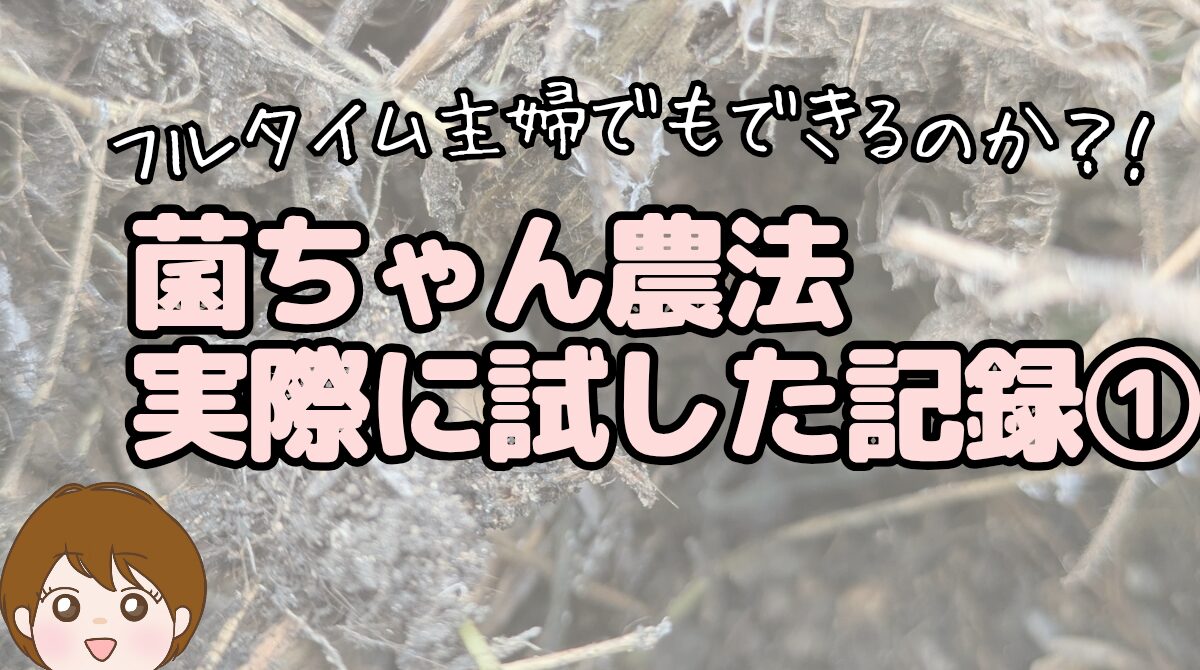
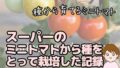
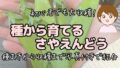
コメント